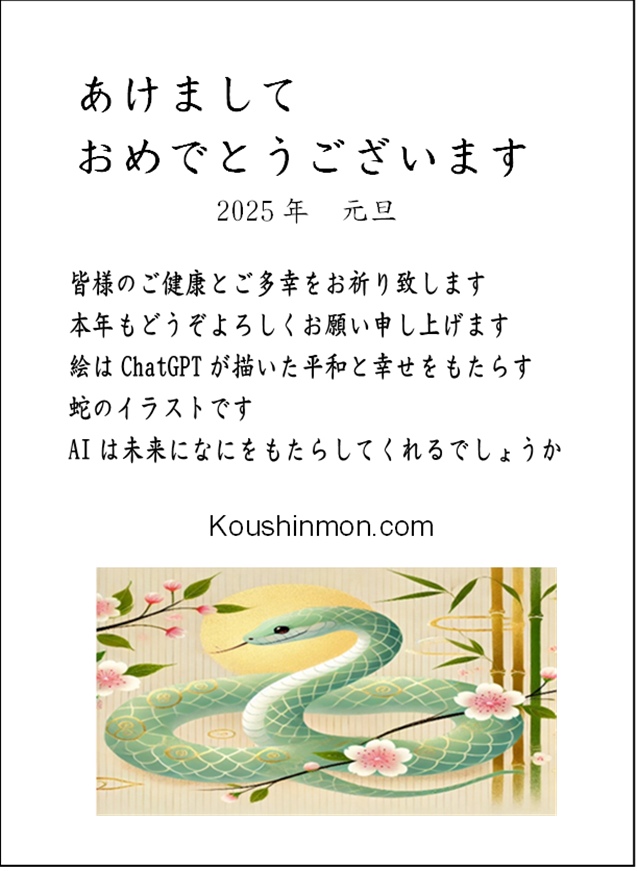市井の日常生活を破壊する戦争は絶対悪ですが、平和の延長線上に戦争が起こることは歴史的事実であり、理論的にも納得できます。
平和が続くと国家間に経済力や軍事力の差、利害紛争、国民の価値観の相違などによる緊張が蓄積し、限界点を超すと戦争が起こります。
例えば、ナポレオン戦争後にヨーロッパで続いた平和の約100年間で蓄積,増大された経済・同盟・国威の競争が、バランスを崩して第一次世界大戦をもたらしました。
ヴェルサイユ条約で目論んだ平和は、ドイツの過剰な経済的負担、国民の屈辱を強いるという緊張を取り切れないものであったので、ナチスの台頭を許し、第二次世界大戦に至りました。
平和時に国家間に生じた経済・軍事・技術力の変動や紛争などから不満や緊張が蓄積され、我慢の限界に達した不満国が戦争で現状の打開を図ることは、不満を持つ国の経済的困窮、国民の屈辱など条件が整えば現実に起こりうることです。
反戦運動は、戦争がプレートの衝突や沈み込みで生じる歪みが限界点を超えると発生する地震のような現実の現象であるとの認識をベースにし、国家間の緊張を緩和、除去する日常的な活動に重点を置くのが良いと考えます。
現在の戦争装置は、国家の行政・軍・経済・民間社会を組み込んだ集合体であり、戦争と平和の境界を曖昧にし、民衆が戦争反対を唱えにくい世界構造にしています。
戦争装置は、直接的な軍事衝突だけでなく、民間社会を組み込み、サイバー戦、民間技術の軍事化、経済制裁・情報操作を行います。
このような環境下では、為政者が国際的な不必要な緊張を招くような発言・行動を行わないように、市民が政治に興味を持ち、為政者の資質、行動を常に注意深くチェックし、社会に向けて自分の考えを示す必要があります。
各分野での生身の市民交流が緊張を緩和し、軍事衝突を防止する強力な反戦活動になります。
各国の民衆が、例えば翻訳機能付きオンラインコミュニティを複数の国を跨いで多数立ち上げ、意見・情報・友好を交換する市民交流も有効な反戦活動になると考えます。
戦争装置はサイバー戦を駆使するので、情報空間の透明性、正確性を確保する活動は緊張を緩和します。
戦争装置は、恐怖・怒り・欲望などの生存の衝動をエネルギーにして緊張を増大するので、それを共存の衝動のエネルギーとして制御し、国および市民が、他と共に成す喜びを実践して戦争装置がもたらす緊張を緩和することが必要だと考えます。